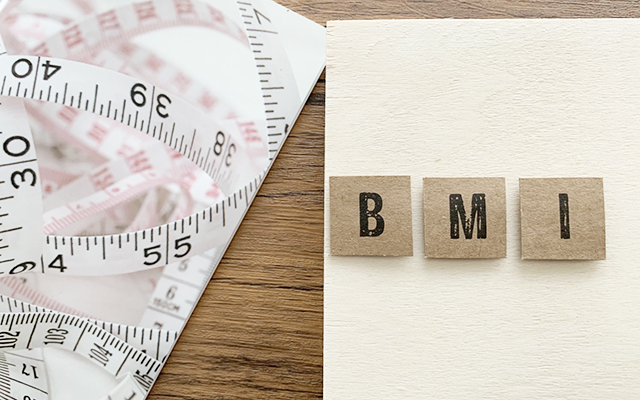「最近ちょっと体重が減ってきたかも…?」
それ、もしかしたら体からのサインかもしれません。
年齢を重ねても元気で動ける体を保つためには、“適切な栄養補給”が欠かせません。
低栄養って何? そのリスクとは
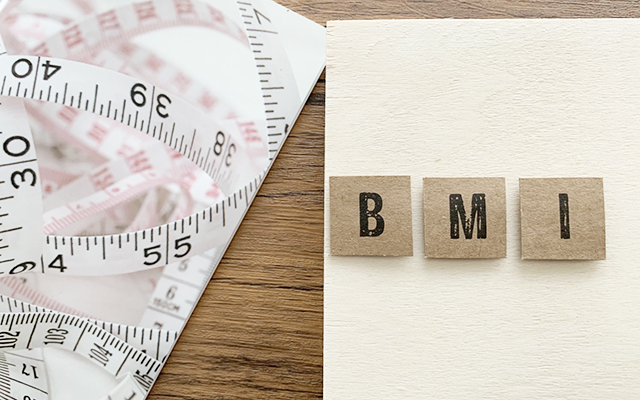 低栄養とは、体に必要な栄養素、特にエネルギー源となるカロリーや身体を作るためのたんぱく質が不足している状態
低栄養とは、体に必要な栄養素、特にエネルギー源となるカロリーや身体を作るためのたんぱく質が不足している状態を指します。
長期的に栄養が足りないと、体重が減少し、筋肉量が減り、免疫力も低下します。
その結果、体力が落ち、感染症にかかりやすくなるなどの健康リスクが高まります。
栄養が足りない状態が続くと…
- 体重、筋肉が減少する
- 免疫機能が低下する
- 体力が落ち、病気にかかりやすくなる
- 傷や床ずれができやすく、治りにくくなる
- 脱水や便秘になりやすくなる
また、肥満度を測るBMI(体格指数 ※)が標準の範囲内でも、必ずしも栄養が十分とは限りません。
エネルギー消費量が減って肥満になりやすい高齢者はBMIも高くなりがちです。
しかし、
見かけ上はBMIが適正でも、栄養不足に陥っていることも少なくありません。
※BMI…身長と体重のバランスを示す指標で、肥満度を簡単に判断するために使われます。
【BMIの計算式】
現在の体重÷[身長(m)×身長(m)]=BMI (18.5〜25 正常)
*65歳以上の目標BMIは、21.5〜24.9です。
高齢者に多い?低栄養に注意したい理由

低栄養に特に注意したいのは、食事に対する意識や習慣が変わりがちな高齢者です。
年齢とともに、以下のような変化が食事に影響します。
-
歯や飲み込みに不安がある
-
味やにおいの感覚が鈍くなる
-
消化機能や基礎代謝が低下
-
食事量が自然と減ってしまう
また、以下のような食生活が習慣化している人も注意が必要です。
-
市販の惣菜・弁当が中心
-
揚げ物や脂っこい肉が好き
-
早食い&満腹になるまで食べる
-
好きな物ばかりを選ぶ
-
洋菓子など間食が多い
加齢とともに消費エネルギーは低下しますが、たんぱく質やビタミン、ミネラルの必要量はそれほど変わりません。
だからこそ、工夫しながらしっかり栄養をとることが大切です。
低栄養を防ぐ食事のポイント

低栄養を予防するためには、毎日の食事に工夫が必要です。
脂質のとり過ぎは肥満の原因に、ナトリウムの取り過ぎは高血圧の原因になりますので、肉(脂身)や加工食品、市販の惣菜は控えめにしましょう。
●たんぱく質をしっかりとる
目標は1食あたり15〜20g程度のたんぱく質を摂取することです。
できるだけ動物性食品より植物性食品を選択しましょう。
*腎臓疾患などがある方は、医師の指示に従ってください。
各食品のたんぱく質量の一例
-
納豆1パック(50g):8.3g
-
もめん豆腐 1/3丁(100g):7g
-
無調整豆乳コップ1杯(180ml):6.5g
-
鮭の切り身(70g):15.6g
-
卵1個:7.3g
-
鶏むね肉(皮なし・70g):16.3g
-
玄米ごはん1膳(150g):4.2g
-
白米ごはん1膳(150g):3.8g
●規則正しく食事をとる
欠食を避け、毎食ごとにバランス良くたんぱく質を含む食品をとりましょう。
●栄養バランスを意識する
たんぱく質だけでなく、カルシウムや各種ビタミン、ミネラルなども必要です。「定食スタイル」が理想です。
●主食も忘れずに
炭水化物はエネルギー源。不足すると、たんぱく質を分解してエネルギー源にしてしまい、筋肉量が減ってしまいます。
●体を動かす習慣を
「毎日40分以上の身体活動」や「1日6,000歩以上」を目標に。家事や外出を増やすことも、身体を動かすよい機会になります。筋肉が強くなると、筋肉に支えられている骨も強くなります。
●口腔ケアも大切
口の中を清潔に保ち、噛みやすく整えることが、食べる意欲にもつながります。
●こまめな水分補給を
食事量が減ると、便の材料や水分が不足します。また、高齢になるほど腸内に悪玉菌が増え、腸の蠕動運動も低下するため便秘になりがちです。
***
食事は“栄養補給”であると同時に、“楽しみ”でもあります。
旬の食材や彩り、香り、器、盛り付けの工夫、ちょっとしたとろみなど、食欲がわく工夫をとり入れてみてくださいね。
【参考文献】
「高齢者の低栄養予防」生活習慣病などの情報(厚生労働省健康づくりサポートネット)
『高齢者の栄養管理』(日本医療企画)
『改訂新版 いちばん詳しくて、わかりやすい! 栄養の教科書』(新星出版社)
『正しい知識で健康をつくる あたらしい栄養学』(高橋書店)
健康づくりのための身体活動・運動ガイド 2023「高齢者版」(厚生労働省)
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年(文部科学省)
【関連記事】

あなたの体と地球を変える?!たんぱく質の役割と効率的なとり方

栄養素を消化・吸収できていますか?

「必須アミノ酸」や「アミノ酸スコア」と耳にするけど、アミノ酸ってどんなもの?

現代人はリンを取り過ぎている?!意外と知らないリンの重要性と過剰摂取のリスク